 |
 |
 |
| Q&A > 投資・運用について |
 |
|
 |
 |
 |
 |

Q1:従業員への投資教育は、誰が行うのですか? |
 |
 |
 |
| A1: |
事業主は企業型年金の加入者に対し、その運用指図に資するため、資産の運用に関する基礎的な資料の提供、その他の必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
但し、この業務は運営管理機関に委託することもできます。
また、運営管理機関(企業が運営管理機関業務を行うことも可能です。)は、提示した運用商品に関する利益の見込み及び損失の可能性、その他、加入者が運用指図を行うために必要な情報を提供しなければなりません。 |
|
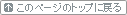 |
|
 |
 |
 |

Q2:自分で運用するということは、どういうことなのですか? |
 |
 |
 |
| A2: |
自分で運用するということは、自分の方針や運用スタイルにあった運用商品を自分で決め、その後の運用状況のチェックもご自身で行う、ということです。
同時に色々な情報を収集し、ライフプランや市場の状況に応じてポートフォリオ(=資産構成)の見直しを行い、資産を成長させることです。
また、確定拠出年金における資産ばかりではなく、ご自身の保有資産全体でお考えいただくことが重要です。 |
|
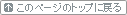 |
|
 |
 |
 |

Q3:どのように運用商品を選んだらいいのかわからないのですが・・・。 |
 |
 |
 |
| A3: |
まずは、運用スタイル診断をお試しいただき、ご自分のタイプを確認してください。
その後、ご不明な点はお気軽に当行にご相談ください。 |
|
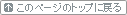 |
|
 |
 |
 |

Q4:いったん商品を選んだら、後は任せておいてよいのですか? |
 |
 |
 |
| A4: |
投資の基本は“長期投資”と言われておりますが、商品を選んだ後はそのままというのは、あまりお勧めできません。
受給可能年齢に近づくにつれ、元本確保型商品の割合を増やすなどして価格変動リスクを減らし近い将来の給付に備えることも必要になるでしょう。
比較的リスクを取れる若い方も、例えば株式市場が高騰して株式部分の評価資産が増大し、ご自分が考えていた運用割合から大きく離れてしまうような場合(=自然に投資リスクのウエイトが変わってしまう場合)もあります。
そのため、定期的に運用スタイル診断のシミュレーションを行い、預替により運用資産のウエイトなどの調整を行なってみることも重要です。
どうしてもご自身で調整するのが面倒だと思われる方は、時間の経過とともに投資割合を調整してくれるライフサイクルファンドとよばれる投信商品を選んでみるのも良いでしょう。 |
|
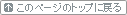 |
|
 |
 |
 |

Q5:どのような情報をどこから収集すればよいのですか? |
 |
 |
 |
| A5: |
まずは、インターネットにて、ご自身の資産状況を定期的に確認していただくことが重要です。
そして、新聞やニュースなど、身近なところから情報を収集したり、インターネットで投資情報が載っているサイトを検索し、研究されるのもひとつの方法です。
|
|
|
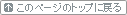 |

