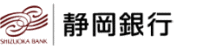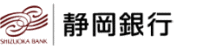|
| ● |
原則:70歳未満の厚生年金保険の被保険者(2022年5月1日〜)
但し、不当に差別的でないとされる場合には、加入対象者を一部に限ることができます。 |
| |
 |
| 【拠出】 |
| ● |
企業は、企業型年金規約に基づき、拠出限度額の範囲内で掛金を拠出します。 |
| ● |
加入者が任意で掛金を拠出できる「マッチング拠出」も2012年1月から認められています。
(ただし、規約で定める必要があります。) |
| 【拠出限度額】 |
| ● |
拠出には限度額を設け、限度額管理は企業が行います。 |
| |
拠出限度額
●DB等の他制度(※1)を実施していない場合:月額55,000円
●DB等の他制度(※1)を実施している場合:
旧制度(※2) 月額27,500円
新制度(※2) 月額55,000円 - DB等の他制度掛金相当額
※1DB等の他制度…厚生年金基金、確定給付企業年金など。中小企業退職金共済、特定退職
金共済はこれに含まない。
※22024年12月以降、拠出限度額にかかる経過措置が適用されている場合を「旧制度」
適用されていない場合を「新制度」と記載し、適用有無は、企業によって異なります。 |
| |
 |
| 【運用】 |
| ● |
加入者は、提示された運用商品の中から自己の年金資産の運用先を任意に選定し、運用指図を行います。 |
| ● |
運用指図は運営管理機関に対して行います。 |
| 【運用商品】 |
| ● |
運用商品は、時価評価が可能で流動性に富んでいるもの。
(預貯金、公社債、投信、保険など。なお、個社株・自社株は可、動産、不動産は不可) |
| ● |
運用商品は3つ以上。
(個別株(自社株を含む)又は個別社債が入る場合には、それらとは別に3つ以上) |
| ● |
元本確保型商品を1つは入れます。 |
| ● |
運用商品の預替頻度については、少なくとも3か月に1回以上実施できること。 |
| |
 |
| ● |
老齢給付金:60歳以降、年金または一時金で受け取ります。遅くとも75歳までに受給を開始しなければなりません。 |
| ● |
障害給付金:障害認定を給付事由とし、年金または一時金で受け取ります。遅くとも75歳までに受給を開始しなければなりません。 |
| ● |
死亡一時金:死亡を給付事由とし、一時金で受け取ります。 |
| ● |
脱退一時金:離転職などにより、制度に加入し得ない者となった場合、加入年数が一定年数以下などの条件を満たせば、脱退一時金の支給を受けることができます。 |
| |
 |
| ● |
少なくとも3年以上勤務する者に対しては全額受給権を付与します。 |
| |
 |
| 【拠出時】 |
| ● |
全額損金算入、かつ従業員の給与とみなしません。 |
| 【運用時】 |
| ● |
運用収益への課税は給付時まで繰り延べられます。 |
| ● |
年金資産を対象として、特別法人税が課税されることになっていますが、現在その適用は凍結中です。 |
| 【給付時】 |
| ● |
老齢給付金:年金受け取り→雑所得課税(公的年金等控除を適用)
一時金受け取り→退職所得課税(退職所得控除を適用) |
| ● |
障害給付金:非課税 |
| ● |
死亡一時金:相続税の課税対象 |
| ● |
脱退一時金:一時所得課税 |
| 【転職時】 |
| ● |
非課税で転職先の確定拠出年金制度に年金資産を移すことができます。
(転職先に企業型の確定拠出年金制度がない場合、または離職した場合は、個人型の確定拠出年金に年金資金を移すことになります。) |
| |
 |
| ● |
詳細はこちら >> |